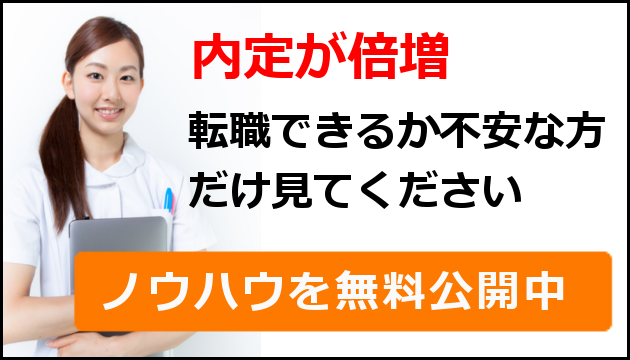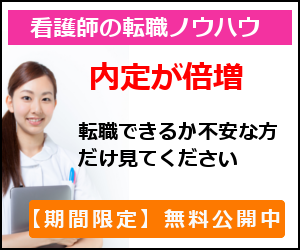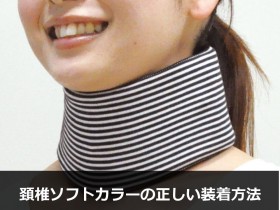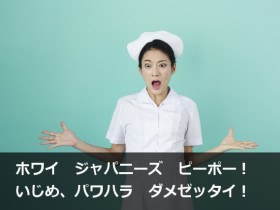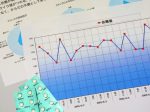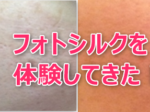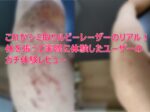読まずにわかるヴァージニア・ヘンダーソンのニード論14のポイント
- 2016/3/21
- 看護学生
- ニード論, ヴァージニア・ヘンダーソン

読まずにわかるヴァージニア・ヘンダーソンのニード論14のポイント
歴史上、多くの看護師が自分の経験から看護とは何かということを考え、看護理論にまとめて発表してきました。バージニア・ヘンダーソンもその一人です。
ヘンダーソンのニード論は、現在の看護にも大きな影響を与えています。ここでは、ヘンダーソンのニード論とその活用について見ていきます。
バージニア・ヘンダーソン
バージニア・ヘンダーソン(1897~1996)はアメリカの看護師です。大家族に生まれ、家族や親せきの多くが第一次世界大戦で兵役に就いたことに影響され、看護の道を志します。
陸軍看護学校で学び、看護師として働いた後、研究者になり多くの著書を残しました。
14の基本的ニード
14の基本的ニードとは、ヘンダーソンの考え方の中でも中心的なものです。
人間の持つ基本的ニードを自分で満たすことができない患者さんに対して、看護師は必要な支援をしていくという考え方です。一つ一つ見ていきましよう。
①正常に呼吸する
②適切に飲食する
③身体の老廃物を排泄する
④移動する・好ましい肢位を保持する
⑤睡眠・休息をとる
⑥適当な衣服を選び、着脱する
⑦衣類の調節・環境の調整により、体温を正常範囲に保持する
⑧身体を清潔に保ち、身だしなみを整え、皮膚を保護する
⑨環境の危険因子を避け、他者を傷害しない
⑩他者とのコミュニケーションを持ち、情動、ニード、恐怖、意見などを表出する
⑪自分の信仰に従って礼拝する
⑫達成感のある仕事をする
⑬遊びやレクリエーションに参加する
⑭正常な発達および健康を導くような学習をし、発見をし、あるいは好奇心を満足させる
ヘンダーソンは、これらのことを満たすために、看護師がどんなサポートができるかということを考えていくことが大切であると説いています。現代の看護にも通じますね。
マズローの欲求段階説
ヘンダーソンの14の基本的ニードの考え方は、マズローという心理学者の欲求段階説というものに影響を受けていると言われています。
人間の欲求を5つのカテゴリーに分類し、階層化したもので、低次の欲求が満たされてはじめてより高次の欲求を求めるという考え方です。
低次から高次の順に、①生理的欲求②安全の欲求③愛と所属の欲求④自尊心の欲求⑤自己実現の欲求と分類されています。
ヘンダーソンの14の基本的ニードと見比べてみると、①~⑧のニードは生理的欲求に、⑨は安全の欲求に対応しているようですね。
基本的ニードも、順を追ってレベルの高い内容になっているようです。呼吸や食事など、生きていくために不可欠なことが満たされて初めて、他者との関わりや自分の生きがいを考えることになります。
実際の患者さんと結び付けて考える
患者さんについて、まずこの14の基本的ニードの視点を中心に観察して、満たされていない問題を見極めます。そして、看護師はどのように援助できるかを考えて計画を立案していきます。
入院中、なかなか眠れないと訴える患者さんがいたとします。まずは⑤の睡眠・休息に問題があるようですね。
しかし、①から順にひとつひとつ丁寧に見ていくと、思わぬところから睡眠がうまく取れない原因が見えてくるかもしれません。
食事の量が多くて苦しい、室温が低くて眠れない、寝間着の着心地が悪い…など、睡眠以外の部分に原因がある場合も少なくないので、一つのことに決めつけないで患者さんの様子をじっくりと観察することが大切です。
もうひとつの主張
ヘンダーソンの主張したことの中でもうひとつ重要なのが、「看護の実践は医師から独立した独自の機能を持つ」ということです。
医師の指示に従うことはもちろんですが、それだけではなく、患者さんのために何ができるかを独立して考え、援助していく存在であるとしています。
一人一人の患者さんをじっくり観察して、細やかなサポートをするというのは、日頃患者さんと多く接している看護師ならではのことです。これも、今に通じる考え方ですね。
最後に
いかがでしたか?ヘンダーソンの看護理論と、これに関わりの深いマズローの欲求段階説についてまとめてみました。
患者さんが基本的なニードを満たすために、看護師は何ができるかを常に考えてサポートしていけるといいですね。古い看護理論からも新しく学ぶことがたくさんあります。参考になれば幸いです。