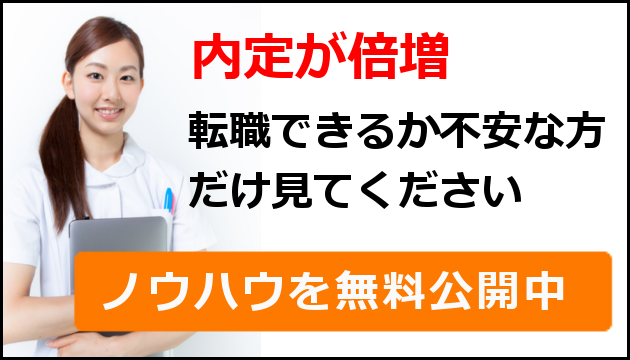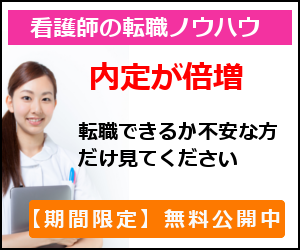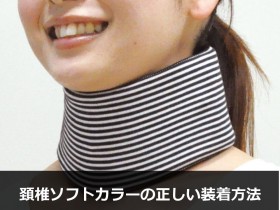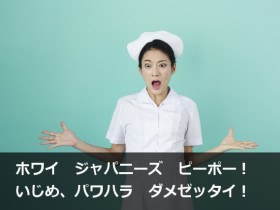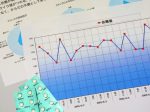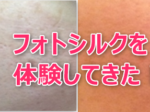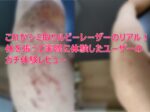P波にQRS波!看護師の心電図への苦手意識を克服する方法
看護師を対象にしたセミナーのうち、かなりの数を占めているのが「心電図」に関するセミナーです。新人看護師ばかりでなく、年齢的にはベテランと思われる看護師もたくさん参加していますね。
心電図は、「苦手、嫌い、避けたい」と思われていることの多い分野です。どうしたらこの心電図アレルギー克服できるでしょうか?分析してみました。
心電図が難解と思われる理由、それは「見えないものを見ようとしているから」
体表面心電図は、心臓の筋肉の動きを電気信号として体表面で感知し、可視化したものです。
つまり、心臓の動きという目に見えないものを電気信号としてとらえ、それを読むことで振動の状態を知る、ということです。
心臓の構造、電気の流れ、拡張収縮の仕組みを理解していなければ心電図を見ても「イメージがわかない」状態となり、わからないのです。興味のない外国語を勉強するようなものです。
心電図を読むことは、「見えないものを見ようとする」高度な技といえます。
心電図を見たときにチェックするポイントを整理しておこう
最初から心電図の全てを理解しようとすると、心電図アレルギーを起こします。不整脈かどうか?を判断できるようなればしめたものです。
最低限のチェックポイントを挙げていきます。
①大きな波(QRS波)の前にP波があるか、P波は上向きか
P波がない場合は不整脈です。P波があれば洞調律です。I誘導で下向きのP波は心電図のつけ間違いか、左胸心・内蔵逆転です。(心臓の位置や内臓の位置が生まれつき逆転している)
②基線の揺れがないか
P波の消失と基線の揺れは、心房細動・心房粗動です。
③P波の後にQRSがあるか
P波だけがありQRSがない場合は、房室ブロックという状態です。
④P波とQRS波の距離が広すぎないか、一定の距離か
房室ブロックの重症度を判定します。
⑤QRS波の幅が広すぎないか
幅広いQRSは脚ブロック等の不整脈です。
⑥QRS波は上向きか
⑦心拍数が正常か、遅すぎ・早すぎないか
ここに挙げたチェックポイントは、かなり基礎的ではありますが、慣れてくるとざっと一目見ただけで異常を把握できるようになります。
心電図を見るポイントを一つ一つ順番に見るように習慣つけていくと、わかる範囲が広がっていきます。
心電図アレルギーの看護師、まずは解剖から理解しよう
心電図が大嫌い!とアレルギーを感じている看護師は、まず解剖を理解することが大事です。今更、と思わずにきっちりと心臓の構造、弁の位置、心臓から出ている血管の位置関係を勉強しなおしてみましょう。
分かっているつもりでも、
- 「肺動脈は何本、どこから出ている?」
- 「大動脈弁はどこにある、弁は何尖で形成されている?」
- 「洞結節はどこにある?」
- 「上行大動脈から分岐する大きな血管は?」
- 「上大静脈・下大静脈と右心房との位置関係は?」
スムーズに答えられますか?
ベースの知識がしっかりすれば、とても心電図がスムーズに勉強できるようになります。
12誘導心電図を勉強すれば、モニター心電図は絶対に読める
解剖を勉強した後に、十二誘導心電図を勉強していきましょう。この時点でアレルギーが出そうになる人が多いと思います。
明らかに異常な心電図を読もうとするのではなく、完全に正常な12誘導心電図をまず「どこが正常と判断するポイントか」をじっくり見ていきます。
正常を、なぜ正常か判断できれば異常がわかってきますよ。
まとめ
いかがでしたか?
心電図を読むことは「見えないものを見ようとする高度な技」です。だからこそ、心臓の解剖を正しく理解することで、かなり「見えて」きますよ。
心電図は嫌い、と諦めないで一緒に頑張りましょう!